新年度を迎え、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
子どもさんの進級や卒業・入学など、新たな門出を迎えられた方もいらっしゃると思います。
新学期といえば皆さん、新しい環境に身を置き、新たなスタートを切っておられることでしょう。
新たな環境の中ではやはり緊張もしますし、うまくクラスやお友だちになじめるか不安を感じている子どもさんもおられるかもしれません。
今回も引き続き、子どもさんの「コミュニケーション能力」についてお話したいと思います。
新年度だからこそ、子どもさんにポジティブな後押しができる親子のコミュニケーションを振り返る良い時期かもしれませんね。
前回は、子どもさんのコミュニケーション能力のベースとなっているのは、家庭の中での【家族との関わり】であるとお伝えしました。
「コミュニケーション能力」といっても、
といったためのノウハウや方法論ではありません。
「人との関係性をどのように築いていくことが幸せなのか」というより根本的な広い視点で、子どものコミュニケーション能力とそれを高めるために必要なことや親にできることを中心にご紹介します。

子どもさんの性格によって、心地良い距離感など人とのコミュニケーションの取り方はそれぞれ。
しかし父母を始めとする家族関係の中で、
「話をちゃんと聞いてもらえる」
「意見や気持ちを言っても怒られない」
「私は大切にされている存在」
という家族への【信頼】と【安心感】を感じられていなければ、社会に出たとき他者とのコミュニケーションに不安を覚えることは自然なことでしょう。
ということで今回は、「コミュニケーション能力のベースとなる他者との【信頼】と【安心感】を家庭の中で育むために、私たち親が自分自身を振り返るポイント」をお伝えしたいと思います。

①自分の対人関係の不安や心配事を子どもに投影していないか?
子どものコミュニケーション能力に強く不安を感じる場合、本当は親自身が過去の経験から人との関わりにネガティブなイメージを持っていることが少なくないでしょう。
「人に合わせないと嫌われる」「一人ぼっちは恥ずかしい」など、親自身が仲間外れにされることを非常に怖れているケースも多くあります。
そして子どものコミュニケーション能力が問題かというよりも、私たち親の方が人との関わりに苦手意識を持っていたり、あるいは現実的に誰かとうまく関係を築けていなかったりすることもあるかもしれません。
そういった自分自身の不安を後回しにしているからこそ、子どもに投影して「お友だちとうまくやれているのか?」と不安になり、心配し過ぎてしまうのです。

自分の“不安や怖れのフィルター”を通して見ているので、本当に子どもがお友だちとの関係で困っているのか客観的に把握できません。
そしてもし実際に困っていたとしても、現実的に子どもがどんなサポートを必要としているか理解できない。
さらには、たとえ小さい問題であっても大きい問題であるかのように捉え、状況や関係性が悪化していくこともあるでしょう。
人は心配事や不安、怖れで心の中に【不安感】が増幅していくと、自身の良さやポジティブな面=「ある」に気付けなくなり、反対に「ない」ばかりにフォーカスしてしまって欠乏感や劣等感、自己否定感が増していきます。
欠乏感や劣等感、自己否定感が増していくと、余計に人を信頼できなくなって人のアラを探すようになり、悪口や文句を言うようになっていきます。
【被害者意識】に飲み込まれ、人とのコミュニケーションはより一層うまくいかなくなってしまいます。

そしてこのような対人関係において、親の【不安感】は子どもへ伝わり連鎖していきます。
子どもが一番不安に感じるのは「親が不安がっている姿を見ること」。
ですから、「親自身が対人関係のどんなところに不安を抱えているのか?」を自覚することが必要です。

②対人関係において「損得勘定」「利害関係」「上下関係」を優先していないか?
損得勘定・利害関係というのは、
などを指し、心の繋がりというより打算的な計算が元になっている関係性です。
「好きだから一緒にいる」のではなく、「メリットがあるから一緒にいる」「不利になるから一緒にいない」というような捉え方で、人として自然な関係性を閉ざしてしまっている状態にあると考えられます。
本来、対人関係というものは「この人のこと好きだな」「なんか合う気がするな」「もっと話してみたいな」と自分の感情や感受性、直感である「好き・嫌い」「快・不快」「心地良い・悪い」という心が感じる感覚に基づいているものです。
メリット・デメリットや損得を軸に置いていては、本当に心が通い合った関係性を築くことはできません。
例えば、親自身がこのような「損得勘定」「利害関係」を優先しているなら、子どもは親の言動や立ち振る舞いから、その価値観を刷り込んでしまい、対人関係においても影響を与えるようになります。
もし子どもに対して「あの子は口が悪いから付き合ってはいけない」と親の損得で注意してしまうと、子どもの自然な感受性に蓋をしてしまうことになり、親が良しとする友だちを選ぶようになってしまいます。
すると心から人と繋がる喜びを感じることはできず、大切な友だちに対してもどう心を開いて接して良いのかが分からずに、人とのコミュニケーションにおいて苦手意識を持つようになっていくでしょう。

人は一人では生きていけません。
人との心地良い繋がりがあるからこそ、孤独から身を守り、安心して生きていくことができます。
そのような【信頼感】や【安心感】のある関係は、打算的な、損得勘定の利害関係では育むことはできません。
子どもに「心が通い合った繋がりを感じられる関係性」を築いてほしいと望むなら、まず現在の自分の在り方に気付き、心が感じる「好き・嫌い」「快・不快」という感性・感情、直感に意識を向けていくことが必要です。

今回も読んでくださり、ありがとうございました。
次回、「コミュニケーション能力のベースとなる他者との【信頼】と【安心感】を家庭の中で育むために、私たち親が自分自身を振り返るポイント」その③、④へと続きます。
読んでくださった方の何かお力になることができたら幸いです。
↓過去のコラムはこちら↓
↓「ライフ」のほかのコラムはこちら↓
平野桂子(ひらの・けいこ)
岡山市在住。3人(高3、中3、小1)の子どもを育てるママ。自身の子育てと介護職に20年間従事した経験から親子関係の大切さに気づく。子育てに悩んだ経験から、同じように子育てで悩むお母さんの力になるべく、現在は心理セラピストとして子育て相談やインナーチャイルド療法、前世療法などに取り組み、より良い親子関係のためのコミュニケーション講座を開催している。2024年春、子どもさんとお母さんの心が楽に、ありのままの笑顔でいられる場所『みんなの家』をオープン。親子で自然と触れ合う参加型の活動を行っている。
心理セラピスト
(子育てでの気付きやヒントなど書いています)
【Instagram】子どもさんがありのままの笑顔で、お母さんの心が楽でいられる『みんなの家』
↓平野さんの紹介コラムもチェック↓
 No.1
No.1
【木下大サーカス】シート紹介2022

【LaLa編集部体験レポ】ママのための就職応援セミナー/おかやまマザーズハローワーク(岡山市)
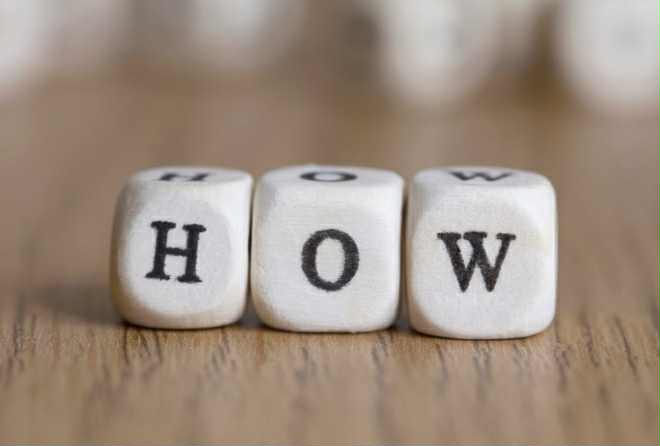
心と繋がるセラピー~お母さんの心が楽になるお話⑦「感情的になっている」と感じるなら…
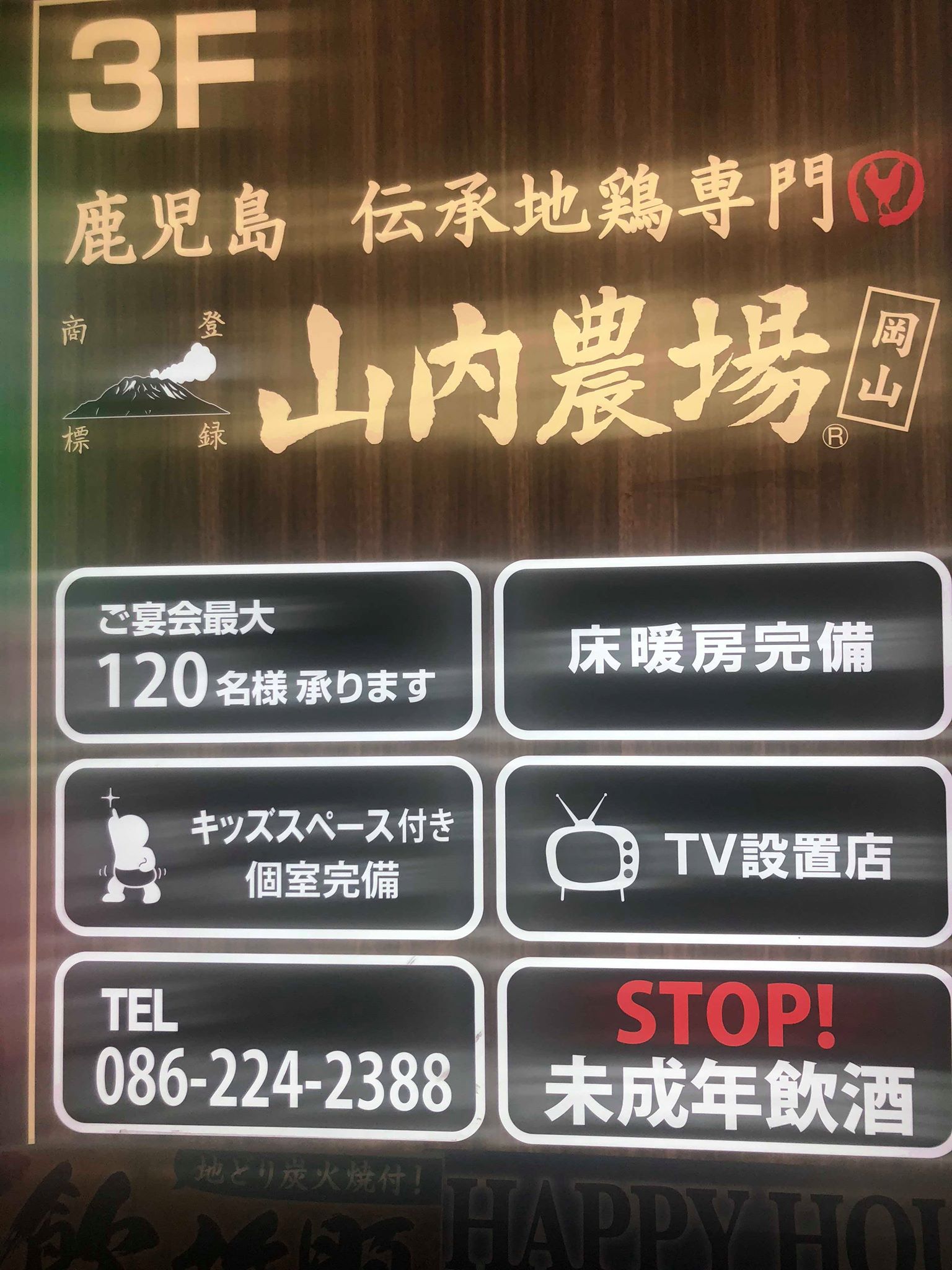
山内農場 岡山駅前店

キラリ★パパさんママさんVol.42大久保愛美さん(総社市、ベビーシッター)
 プレゼント
プレゼント
