赤ちゃんは、胎児のころから指しゃぶりを通じて哺乳を練習します。
さらに出生後も、手と口を協調して動かして離乳食を食べる練習として、指しゃぶりは赤ちゃんの成長発達に必要な過程です。
一方、長期間続くと歯並びや噛み合わせ、口呼吸、発音など、お口の機能に影響する可能性も。成長発達に合わせ、“卒業”していくことも必要です。
・胎児期=哺乳の練習
・乳児期前半=哺乳から離乳食への準備
口と手の協調運動の発達を促し、口を刺激することで哺乳に必要な反射が徐々になくなります。
そして自分の意思で口を動かすことを学んでいきます。
・乳児期後半=食べる・飲む機能の発達と気持ちのコントロール
唇で食べ物を取り込む、口を閉じて飲み込む、噛むことを学びます。
行動範囲が広がりいろいろな物に手を伸ばすようになるにつれ、空腹や眠いときに気持ちを落ち着かせるため指しゃぶりするようになります。
・幼児期前半(乳歯列完成前)=機能発達的には特に意味がなくなる
話すことで口、遊ぶことで手を使うようになり少なくなりますが、無意識の癖やストレスへの対処法として指しゃぶりをする場合も。
・幼児期後半
お口の形や機能への影響、特に学童期以降は顎の発育や歯列への影響も生じやすくなります。
癖やセルフコントロールとして残っている指しゃぶりを「やめようとする意識」を育てることが大切になります。
・1歳ごろまで=発達過程における生理的行為なので見守る
手指だけでなくおもちゃや身の周りにある様々な物を口にして確かめ、自分の世界を広げていきます。
衛生など口遊びができる環境を整え、積極的にスキンシップを図ることで発達をサポートしましょう(身体だけでなく顔や唇、慣れてきたら口の中や舌にも優しく触れてみます)。
・1~2歳=見守ることが基本。でも長時間続く場合は対応を
コミュニケーション、手指を使う遊びや身体を動かす外遊びが増え、指しゃぶりの頻度が自然と減っていきます。
長時間続く場合、「声がけしてコミュニケーションを増やす」「スキンシップを図って気持ちを落ち着かせる」「手指を使う遊びや外遊びに誘う」など、少しずつ頻度を減らす関わり方で習慣化しないようにしましょう。
・3歳~=頻度を減らすサポートが必要に
生活リズムが不規則な場合は整える。
動画の試聴時間を減らし、外遊びなどでエネルギーを発散させます。
親子のふれあいや同年代の子どもたちとの遊びの機会を増やすことも大切。
歯並びなどへの影響をわかりやすく伝え、自覚を促すことも効果があります。
指しゃぶりが再発した場合、弟妹の誕生、母乳や哺乳瓶の中止など、原因を考え、その子に合わせた対応を心がけましょう。
心配や不安から親が子どもを叱責することは、あまり効果があるとはいえません。
小児科医や小児歯科医、臨床心理士などに相談し、適切にサポートすることが大切です。
今回は、ご相談の多い指しゃぶりへの対応についてお伝えしました。
理由を知ることで、乳児期には不安のない見守り、そして運動機能や精神、社会性の発達といった成長に合わせた環境整備による“卒業サポート”の参考になれば幸いです。
発達スピードや個性は子どもによってそれぞれ違います。
難しいと感じるときは親御さんだけで抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。
↓過去の記事はこちら
↓「育てる」のほかの記事はこちら
・ママ楽♪おやこの作り置き/かんたん“時産”ごはんのススメ⑨保育園メニューかみかみサラダ
・初めての育児 in 岡山/0~1歳ママ応援特集/一年間の成長過程を追う/11月
横道由記子
子どものころ、むし歯だけでなく歯並びに悩んで矯正治療を受けた経験から「予防歯科」という言葉に引かれ、地元岡山大歯学部で学び平成25年和気歯科医院長となる。
むし歯予防だけでなく、噛み合わせにおいても原因を見つけ治療と合わせて予防していく考え方を学び、医院では我が子の子育てで悩み学んだことを生かして小児歯科・小児矯正歯科を担当。
地域の幼・保育園、公民館での子育て支援事業や、企業主催の教室などで健康なお口と心身を育むサポートを積極的に行っている。
授乳、抱っこ、離乳食、むし歯予防、歯並びのことなど、歯医者さんに聞いてみたいことを公式LINEから無料で相談できます。
↓↓ハピリスキッズクラブが生まれた和気歯科・小児歯科の情報はこちら
 No.1
No.1
子連れでしっかり遊べる!「岡山オススメ公園ナビ」⑱/穴場感満載!?新設遊具が目を引く伊部運動公園(備前市)

子連れでしっかり遊べる!「岡山オススメ公園ナビ」⑰/水遊びの季節!おまちアクアガーデン(岡山市中区)

オトナが見えているようで見えていない!子どもの本当のキモチ/③一枚の絵からこんなことまでわかっちゃう!「おえかき」は心のバロメーター
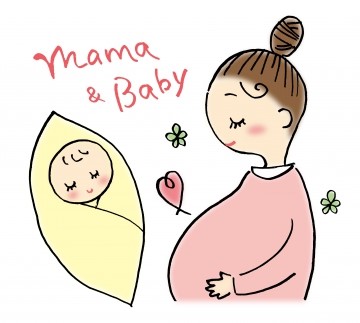
1~3歳ママ応援特集/一年間の成長過程を追う/6月

理学療法士ママの「赤ちゃんの成長発達で大切にしたいこと⑫【発達を応援するって?】(最終回)
 プレゼント
プレゼント
